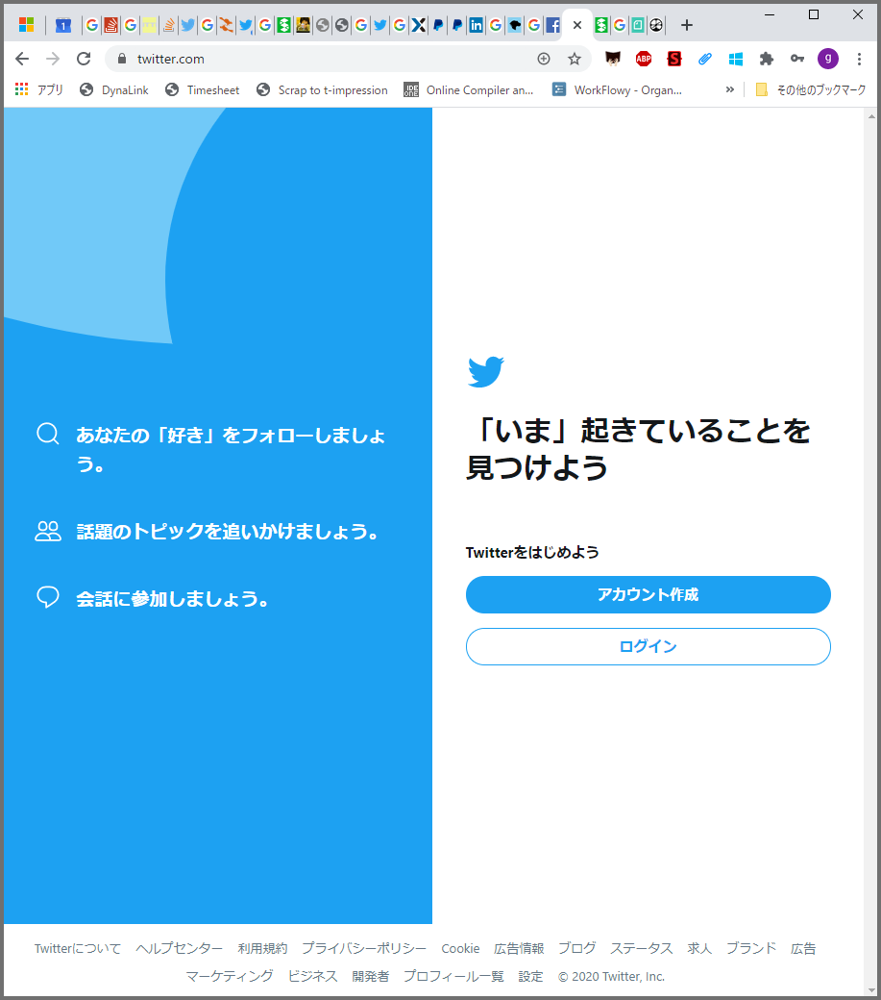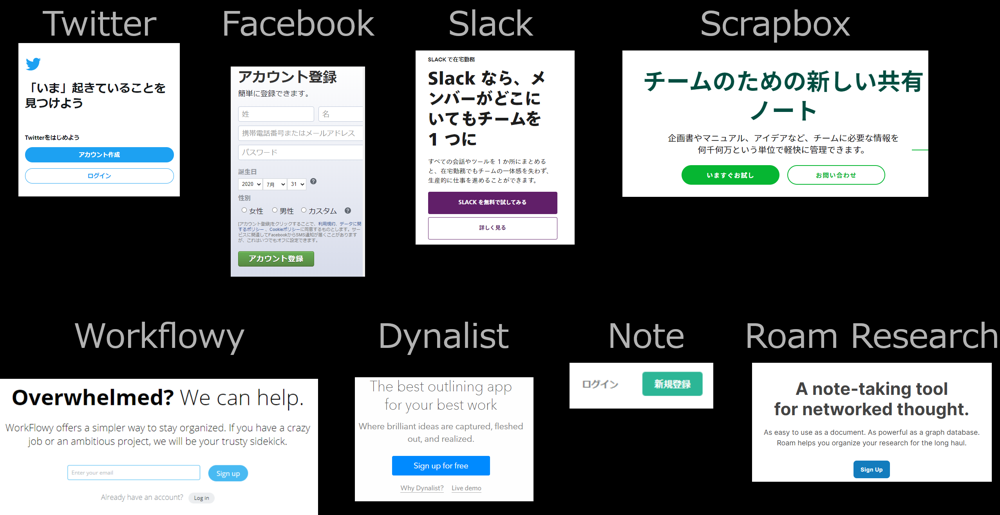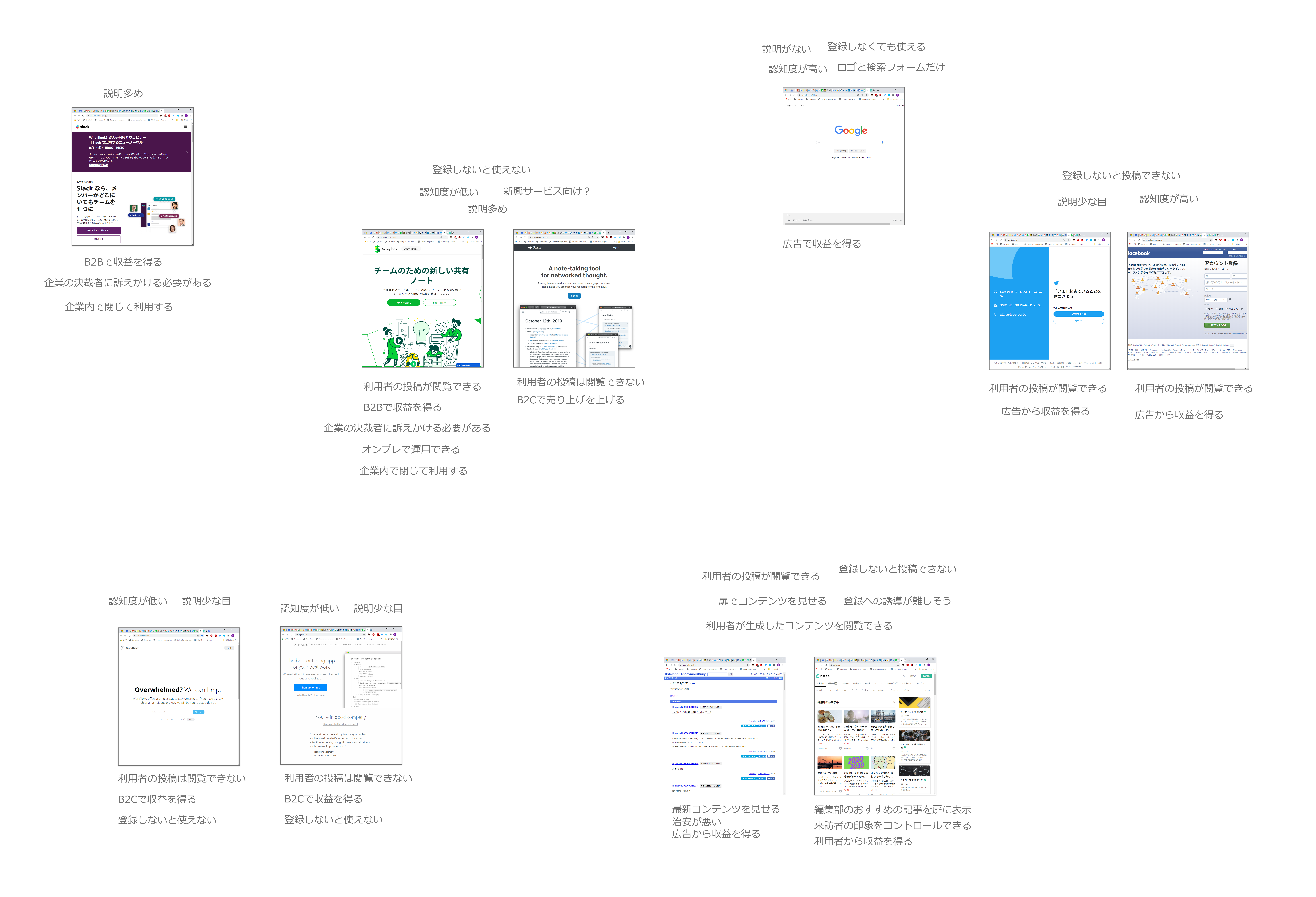user interface
UI層から実装を進めると、無駄な機能の開発が省かれる上に、ユーザーからのフィードバックを早期に得られ...
失敗したときに損失が大きい操作と業務を現すUIに力を入れる
あれ
iOSの画面下からスワイプしてアプリ切り替えるやつ、早くスワイプすると早くアプリ切り替えモードになる。私だったら単純に位置で閾値を設定する。その方が楽だから。でもAppleはそうしてない。怖い。
気持ちの良いUIにするために、機械学習で判定してんじゃないかとすら思わせられてしまう。
iPadでは四本指で横にスワイプするとアプリを切り替えられる。謎に気持ちが良い。マジ謎。
『気持ちよいUIができたら後は放置。傑作Flash『艦砲射撃・マテスナ』作者の素敵な“悪癖”【フォー...
OOUI
あれ
note AIアシスタントにはGPT-3使ってるらしいけど、ChatGPTのGPT-4使えば良くない?ってなってる。UI次第か。書き心地の良いものだったら使う意味ありそう。どう統合を取るのかが見ものだ。
『UIから「白」が消える日』
UIデザイン
デライトのボトルネックはUI?
もっとわかりやすくすれば利用者が増加する?どうすればわかりやすくなるかはわからない。
あれ
あれ
=}ボタンを意図せず触ってしまって、操作を失敗しているのが気になった。マウスオーバーで要素のサイズが変わって配置が換わってしまうのはよくないのかもしれない。
Scrapbox・デライトのUIはまだ標準的な方だと思う
- Microsoft OfficeのリボンUIに比べれば、Scrapbox・デライトのUIはまだ標準的というか、一般的によくあるものの範疇に納まっていると思う
- ただ、MSのUIについては初めてパソコンに使う人が使いやすいことを目標としているはずなので、独自性は問題にならない
- 以前、PCをほとんど使っていない人を対象に、UIをテストしているというのを聞いたことがある
- 開発者の家族をテストに使っているとか(言及された文書がないか探してみたい)
- 最もわかりやすい(と思える)UIを追求できる
- 普及しているので、「俺が標準だ」ができる
- 他の情報整理系のアプリに関しても、もっと独自性の強いUIパーツを使っていることがよくある
あれ
『融けるデザイン』が、発想の元になっています。
そのものズバリの記述はないですが、UIは存在感を無くすことが重要だと書かれています。
以下『融けるデザイン』より引用
「透明性」とは、道具を意識しないで利用できることである。ではなぜ道具を意識しないで利用できることが重要なのか?
ハンマーであれば釘を打つことができ、それは手では到底できない。このように、人の力を拡張する、にもかかわらず実際に利用し始めるとそれ自体を意識しなくなるのだから、いわば何も持ってないのと同じ、つまり自分の身体と同じような感覚でその力を利用できるのである。
これと同じように、道具が透明化するということは「自分の身体と同じような状態」になるのである。そしてこの意味において、道具は「身体の拡張」と呼ばれる
集客
UIの存在感
今、集客が必要なサービスでは、衆目を集められるようなUIの方が良いのだろう
集客が終わったサービスでは、空気のような存在感のないUIがいいのかもしれない
全知検索ボタンのUIアニメーション
Roam Researchがどう言った記法を使っているか気になってきた
Roam Researchがどう言った記法を使っているか気になってきた
角括弧を二つ重ねることで、リンクが貼れることしか知らない
二重角括弧
記法
あれ
デライトはHTMLを書ける点で、Scrapboxよりも標準的な記法を使っている
HTMLを書くのが大変というのはあるので、標準的だけど利用者は限られる
リボンUI
基本的にScrapboxは独自記法を気にしなくても使えるようになっている
基本的にScrapboxは独自記法を気にしなくても使えるようになっている
UIで入力を補完できる
独自記法を使いたくない人が困るのは、他の人が書いた行を編集するときぐらい
新規に書くときは平文で書いてしまえばいい
良い内容だったら、独自記法に精通した他の人がScrapbox記法に編集してくれる
暗黙的なアクション
あれ
ゼロから考えると、
- サイトのロゴを押下→ホームに遷移
というのは暗黙的な挙動になっている
アプリ起動時との操作の一貫性を持たせている?
- アプリアイコンを押す→ホームに遷移
- サイトのロゴ(アイコン)を押す→ホームに遷移
Twitterっぽいデライト扉案
扉のアカウント登録用パーツを比較
SNS型の利用者登録誘導
| 行動1 | 検索・リンク経由でコンテンツを見る(サービスに興味を持つ) | →トップページに移動する | →利用者登録する |
|---|---|---|---|
| 行動2 | 知人から誘われる(サービスに興味を持つ) | →Googleで検索してトップページを表示 | →利用者登録する |
利用者登録数=コンテンツ数×コンテンツへの流入率×利用者登録のしやすさ
コンテンツへの流入率向上のための施策: SEO対策・コンテンツ共有機能の充実(Twitter: ツイート埋め込み機能, ブログ: ツイートボタンなど)
サービス名で検索する人の大体は利用者登録したい人(のはず)。扉は利用者登録に特化させた方が利用者の目的と合致する。
登録していない利用者からも収益を得るサービスは扉でコンテンツを前面に出す
認知度が上がるとサービスの説明が減る
Google: ロゴと検索フォームだけ、すぐに検索ができるようになっている。このページ自体の利用頻度は低そう。
Facebook、Twitter: アカウント作成のボタンを最も強調する。すぐにアカウント作成できるようになっている。それ以外(ログイン、説明)は強調しない